メタバースECとは?注目される理由やそのメリット、活用事例を紹介
- 2025.02.10
- EC
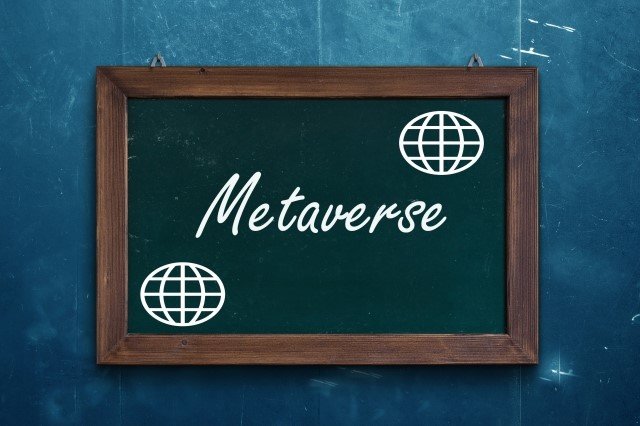
オンラインでの消費活動が増えていくなかで、新たな販売手法としてメタバースECが注目を集めています。しかし、メタバースECが具体的にどのような手法なのか詳しく知らない方も多いでしょう。
メタバースECは仮想空間内で行われる電子商取引で、今まで接点のなかった新しい顧客層にアプローチできるなど多くのメリットがあります。
今回はメタバースECについて注目される理由やメリット、活用事例を紹介します。
本記事を読むことで、メタバースECの概要を理解してスムーズに導入が可能です。
メタバースECとは何か
 メタバースECとは、主に仮想現実の3D空間で行われる電子商取引です。メタバースはインターネット上に構築された仮想空間の総称で、アバターを使ってほかのユーザーや環境と自由に交流できる特徴があります。
メタバースECとは、主に仮想現実の3D空間で行われる電子商取引です。メタバースはインターネット上に構築された仮想空間の総称で、アバターを使ってほかのユーザーや環境と自由に交流できる特徴があります。
EC(電子商取引)は商品やサービスを購入・販売する活動を指し、メタバースECは従来のECサイトとは異なり、没入感のある体験を提供できる点が特徴です。ユーザーは、実際の店舗を歩き回るように商品を選んだり、リアルタイムで店員アバターに質問したりできます。
メタバースECは単なる買い物の場ではなく、体験型の消費活動を可能にする新しい市場として注目されています。
メタバースとVRやAR、MRとの違い
メタバースとVR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)は似ているようで異なる概念です。VRは「Virtual Reality」の略で、完全に仮想の世界に没入する技術であり、ゴーグルなどのデバイスを使い、現実から切り離された3D空間を体験できます。
一方、ARは「Augmented Reality」の略で、現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術です。スマートフォンや専用のメガネを使い、現実世界に仮想的な物体や情報を表示します。
そして、MRはARをさらに進化させたもので、仮想のオブジェクトに対して現実的な操作が可能です。たとえば、仮想的なスイッチを押したり、物体を動かしたりする体験が実現します。
メタバースECとバーチャルショップは違う?
メタバースECとバーチャルショップは似ていますが、指す範囲が異なります。メタバースECとは、メタバース空間内で行われる電子商取引全般を意味します。商品を購入したり、サービスを受けたりする行為そのものがメタバースECです。
一方で、バーチャルショップはメタバース空間内に存在する店舗そのものを指します。実際のショッピングモールや小売店の仮想版と考えると分かりやすいでしょう。つまり、メタバースECは「消費活動全般」であり、バーチャルショップは消費活動が行われる「場所」に当たります。
なぜ今メタバースなのか、活用するメリット

近年、メタバースが注目される背景には、新型コロナウイルスの影響が挙げられます。リモートワークやオンライン会議の普及により、人々がインターネットを介してつながることに抵抗を感じなくなりました。さらに、仮想空間での活動に慣れて新しいコミュニケーションの形が受け入れられるようになっています。
たとえば、仮想オフィスを利用した会議やイベントの開催などがメタバース活用の例です。上記の流れを受け、メタバースは新しいビジネスや生活の場として成長を遂げています。特に企業にとっては、新しい市場への参入や顧客との接点を広げるための有効な手段となっています。
メタバースを活用するメリット
メタバースを活用すれば、企業は以下のような多くのメリットを享受できます。
- 新規顧客の開拓につながる
- 新しい企業姿勢を示すことができる
- 実店舗を借りるまでのコストがかからない
上記のメリットに魅力を感じる場合は、メタバース導入を検討しましょう。
1. 新規顧客の開拓につながる
メタバースの大きな魅力は、新規顧客の獲得が期待できる点です。メタバース内には多種多様な店舗が隣接して存在し、ユーザーは自由に移動して買い物を楽しめます。そのため、今まで接点のなかった新しい顧客層にアプローチしやすくなる点がメリットです。
特に、実店舗に比べて来店への心理的なハードルが低く、興味を持ったユーザーが気軽に店舗を訪れられます。また、店舗のデザインや商品ディスプレイに工夫を凝らせば、ブランドに興味をもつユーザーを効果的に引き寄せられます。
2. 新しい企業姿勢を示すことができる
メタバースを活用すれば、企業は新しい姿勢や価値観を顧客に伝えられる点がメリットです。たとえば、アパレル商品を販売する店舗の場合、実際の商品を手に取ることが難しい状況でもアバターに試着させて商品の魅力を伝えられます。
また、バーチャルショップのデザインを季節やブランドイメージに合わせて変更すれば、リアル店舗では難しい細やかな表現も実現が可能です。上記の取り組みにより、企業は顧客に対して革新的な姿勢をアピールし、ブランドイメージの向上につなげられます。
3. 実店舗を借りるまでのコストがかからない
メタバースを活用すれば、企業は実店舗にかかる多くの運営コストを削減できます。たとえば、テナントの賃貸料や水道光熱費、店舗スタッフの人件費などは必要ありません。そのため、限られた予算で新しいビジネスを始めたい企業にとって大きな魅力です。
また、実店舗を持たない企業がバーチャルショップとしてメタバースに参入するケースも増えています。比較的規模の小さい事業者でも、メタバース内で顧客との接点を持ちやすくなる点は大きなメリットです。
メタバースでECを利用する上で運用ポイントと課題

メタバースには多くのメリットが存在しますが、一方で運用にあたっては押さえるべきポイントや課題もあります。メタバースECを成功させるためには、適切な運用設計や明確な目的の設定が欠かせません。
また、メタバースECにおける課題を理解して対応するための取り組みを進めることも重要です。本章では、メタバースECを運用する際のポイントと事前に検討すべき課題について解説します。
メタバースでECを運用するポイント
メタバースでECを運用する際には、従来のECや実店舗とは異なる視点が求められます。メタバースの特性を生かし、利用者の方に新しい体験を提供することが鍵です。また、目的やターゲットを明確にして知名度を高めるための戦略も重要で、以下では具体的な運用ポイントについて解説します。
1. 実店舗ともECとも異なる体験を設計する
メタバースでのECが注目される理由は、没入型の体験を提供できる点です。たとえば、仮想空間内で商品を3Dで試着したり、商品に関連するイベントをリアルタイムで開催したりするなどの体験が考えられます。
また、ユーザー同士がコミュニケーションを取りながら買い物を楽しめる仕組みの構築も可能です。
実店舗や従来のECサイトと同じ体験を提供するだけでは、ユーザーに強い興味を持ってもらうのは難しいです。
メタバースならではの特性を生かし、新鮮でユニークな体験の提供が成功の鍵となります。
2. なぜメタバースかという活用の目的やターゲットを明確にする
メタバースを導入するだけで売上が急激に向上するわけではありません。成功のためには、「メタバースをどのように活用するのか」を明確にする必要があります。
たとえば、特定の年齢層や趣味嗜好を持つターゲット層に向けたブランディング、従来の市場では届かなかった層へのアプローチなどが考えられます。
また「メタバース内での活動を通じて何を実現したいのか」の明確化も重要です。
曖昧な目的のまま進めると、メタバースの導入で期待されうる効果が得られないおそれがあります。
3. メタバース店舗としての知名度を上げる
メタバース内には数多くの店舗やコンテンツが存在し、注目を集めるには店舗の認知度を高める努力が欠かせません。たとえば、メタバース内でのイベントに参加し、ブランドや店舗の存在を積極的にアピールすることが効果的です。
また、外部のSNSや広告を活用してメタバース店舗の魅力を広く発信する方法もあります。さらに、既存の顧客を巻き込むキャンペーンやメタバース専用の商品展開なども効果的です。知名度を上げれば、より多くのユーザーに来店してもらえるようになります。
メタバースでECを利用していくにあたっての課題
メタバースでECを展開する際には、技術的な課題やユーザー体験の面での課題が存在します。特に、利用環境や操作性に関するハードルは利用者の方の拡大に影響を与える要因です。以下では、メタバースECを利用する上での主な課題について解説します。
1. 没入体験のための機器の一般普及
メタバースを最大限に楽しむには、VRゴーグルや専用デバイスなどの高度な機器が必要となる場合があります。しかし、上記のデバイスは現在のところ価格が高く、一般的な普及率も十分ではありません。
メタバースを利用できるユーザー層が限定されてしまう課題があるため、低コストで気軽に利用できる環境の整備が求められています。今後、価格の低下や技術の進化により普及が進めば、さらに多くのユーザーがメタバースを利用するようになるでしょう。
2. UIのわかりづらさ
現在のメタバースは、操作性において課題を抱えている場合が多いです。特に、初めて利用するユーザーにとってはインターフェースの分かりづらさが利用のハードルとなっています。
たとえば、メタバース内での移動やアイテムの購入が簡単に行えないとユーザーが煩わしさを感じてサービスから離脱してしまうおそれがあります。上記の課題を解決するためには、簡単で分かりやすいUI設計がメタバースに必要です。
メタバースECの事例
 メタバースの進展に伴い、多くの企業が仮想空間でのEC展開を進めています。以下に、メタバースECに取り組む企業の事例を3社紹介します。
メタバースの進展に伴い、多くの企業が仮想空間でのEC展開を進めています。以下に、メタバースECに取り組む企業の事例を3社紹介します。
【事例①】大手百貨店
この大手百貨店では、独自のメタバースプラットフォームを開発し、仮想空間での新たな顧客体験を提供しています。上記のプラットフォームではアバターを通じて店員と顧客がコミュニケーションを図り、実店舗さながらの接客をオンライン上で実現している点が特徴です。 また、友人や家族と一緒にメタバース空間でショッピングを楽しめるため、従来のECサイトでは得られない偶然の出会いや発見を提供しています。VRヘッドセットなどの専用機器は必要なくスマートフォンからアクセスできる手軽さもあり、幅広いユーザー層に対応しています。
【事例②】大手アパレル会社
この大手アパレル会社ではVR技術を活用したバーチャル店舗を展開し、オンライン上での新たな購買体験を提供しています。上記の取り組みにより、ユーザーは自宅にいながら店舗を訪れ、商品の閲覧・購入が可能となりました。 さらに、バーチャル店舗での体験が実店舗への来店動機となり、オンラインとオフラインの相乗効果を生み出しています。上記のように、メタバースを活用してブランドの魅力を多面的に伝え、顧客との新たな接点を創出しています。
【事例③】大手シューズメーカー
この大手シューズメーカーは、自社のメタバースプラットフォームを開設し、仮想空間でのブランド体験を提供しています。ユーザーは自身のアバターにシューズメーカーの製品を装着し、メタバース内でミニゲームやショールームなどのエンタメコンテンツを楽しめるのが特徴です。 また、仮想スニーカーデザインを手がける会社を買収し、デジタルスニーカーを販売するなど商品開発にもメタバースを活用しています。上記の取り組みは、デジタルネイティブ世代との接点を強化し、新たな市場開拓を目指す戦略の一環といえます。
まとめ
メタバースECは、仮想空間での新たな購買体験を提供する次世代の電子商取引です。新型コロナウイルスの影響でオンラインコミュニケーションが一般化し、仮想空間での活動が活発化しました。
メタバースならではの没入型体験や新規顧客開拓、低コスト運営が注目されていますが、一方でVR機器の普及率や操作性の課題も指摘されています。メタバース活用の成功には独自の体験設計や明確なターゲティングが重要です。



