ウェブアクセシビリティが当たり前の社会をともに実現する――KivaとBIPROGYが『ユニウェブ』活用で目指す世界【後編】
- 2025.03.19
- 特集

ウェブアクセシビリティツール『ユニウェブ』を展開する株式会社KivaとBIPROGYが語り合う、日本のウェブアクセシビリティの現状や課題についての対談インタビュー。前編では、すべての人が自分に最適なものを選べる状態とは何か、日本企業が今どのようにウェブアクセシビリティに取り組んでいるのかについてお話しいただきました。後編では、協業の意義やその根底にある思い、そしてすべての人々が企業サイトを活用できる社会へのムーブメントについて話が及びました。
実績の多さが何よりの証拠。協業によりさらなる展開へ

小売業界ではコントラスト切り替え機能の利用率が高い
――BIPROGYにとって、Kiva様の『ユニウェブ』と協業することの魅力はどのように感じていますか?
横山:ユニウェブの1番の魅力は、確かな実績をお持ちであることだと思っています。特に、弊社のお客様に多い「小売での事例があるかどうか」は協業の大事な視点でした。実際に弊社のセールスからも、ユニウェブについて「御社と同じ業種の大手企業も、ユニウェブを導入していますよ」と説明すると納得いただけることが多いと聞いています。
事例が多いということは、経験値を積まれているということ。何かを相談した時にも「あの時はこうした」というノウハウをお持ちなので、安心感があります。
磯崎:ありがとうございます。『ユニウェブ』の最初の実績は、先にリリースしていたECサイト向け延長保証サービス『proteger(プロテジャー)』でつながりがあったEC事業者様でした。そこから小売業界に広がっていった経緯があります。
齊藤:私がセールスとして接する中でも、どういった業種がサービスを導入しているかを気にされる企業様は多い印象があります。海外でのウェブアクセシビリティの浸透や、日本が海外基準に準じていく方向性は企業様も理解されていますので、私たちには「それを実行する」という判断の後押しをさせていただく役割があると思っています。
無料トライアル期間を設けて実際に体験していただくと「サイトに1行のタグを設置するだけで、こんなにいろいろな機能が使えるんだ」とお褒めの言葉をいただくことが多いですね。
――ウェブアクセシビリティ導入の効果はどのように測定・評価されているのでしょうか?
磯崎:実装したウェブアクセシビリティに関して、「どの機能が1番使われているか」や「この業界ではこの機能の利用率が多い」などのデータがあります。例えば、小売業界ではコントラスト切り替え機能の利用率が高い傾向にあります。
ウェブアクセシビリティの導入は、自社の姿勢の表明ともなる
――今の日本において「ウェブアクセシビリティに対応していること」は、企業の1つの強みとなるのでしょうか?
磯崎:競争力の1つとなる可能性はあると思います。とはいえ、グローバル企業は既に当たり前にウェブアクセシビリティを導入しています。例えば大手ファストフード店では最近、サイネージのような大きな画面で注文ができますが、車椅子の方やお子様でも操作できる高さに画面を切り替えることができる設計になっています。
横山:「今までウェブアクセシビリティの問題で購入されていなかった、障がいのある方からも購入いただくことができれば、売上は上がっていく」という発想で取り組んでいるグローバル企業は多いのではないでしょうか。動機はさまざまですが、サポートを必要とする人たちに対してきちんと配慮するという姿勢は重要だと感じます。
磯崎:そうですね。日本でも合理的配慮の提供は義務化されたものの、現状の罰則は重くはありません。ただ私は、今後大きく流れが変わると予想しています。
横山:ウェブアクセシビリティによるサポートが当たり前のこととして普及していくことは、健常者と障がい者の差が埋まっていくことにつながるのかもしれません。
磯崎:ウェブアクセシビリティに限らず、日本は法令対応が遅くなりがちな印象があります。しかし障害者差別解消法の改正後、「合理的配慮」という言葉も認知されはじめています。
また最近では、いわゆる「炎上」がしばしばニュースになっています。例えば、公園内を走行するバスが、盲導犬を連れた視覚障害者の乗車を断ったこと、映画館で従業員が車椅子ユーザーの介助を断ったことなどが、SNS等で炎上しました。判例と同様に炎上も、時代を動かすひとつのトリガーとなるだろうと考えています。
現時点では、ウェブアクセシビリティの対応が早い業界は、BtoCのサイトである小売だと感じています。実際に、1万件以上ある海外の訴訟事例のうち80%以上が小売業界だと言われています。
協業の根底にあるのは、互いの"思想"への共感

ウェブアクセシビリティが当たり前の社会を、ともに実現したい
――今回、Kiva様とBIPROGYの協業が実現しました。それぞれ、どのような効果を期待されていますか?
磯崎:BIPROGY様は大企業のお客様を数多く担当されています。今回の協業によって、エンドクライアント、BIPROGY、Kivaが三方良しの形になりつつ、ウェブアクセシビリティを世の中に広げるスピードを加速させることができれば良いと考えています。
横山:BIPROGYは、昔から教育や金融、自動車業界など幅広い業種・業界のクライアントを担当しています。当社にとっても、それらのクライアントから「ウェブアクセシビリティってどうなの?」と顧客から相談を受けた際に、いつでも『ユニウェブ』をご紹介できるというのは望ましいことです。また、単にサービスを使う・使わないだけではなく、コンサルのようなことも含めご一緒できることで、当社もウェブアクセシビリティの知見を得ることができます。
企業間の協業では、両社の目指すものへの共感が重要ですよね。今回の協業は、Kiva様の知見やノウハウがBIPROGYにとって魅力だったということももちろんありますが、何よりも対話の中で、その「思想に共感した」ということから実現したものです。事例を持つKivaとネットワークを持つBIPROGY、互いの存在が武器になると思います。もちろん売上や利益も大切ですが「ともにウェブアクセシビリティが当然とされる社会の実現に貢献ができる」という意義は大きいと考えています。
――最後に、今後の展望についてお聞かせください。
磯崎:2025年1月、『ユニウェブ』では画面共有機能をリリースしました。画面共有ボタンを押すことで、既存のウェブ会議システムなどを活用することなく、オペレーターとやり取りができるものです。オペレーターがお客様の画面を見て操作・入力ができますので、全盲の方でもECサイトで買い物ができるようになります。他にも、ウェブサイト自体の多言語翻訳の対応も開始しました。
Kivaとしては、ウェブアクセシビリティの規格に向き合うフェーズは、既に一定程度終わりつつあると考えています。今回の協業のような、社会全体にウェブアクセシビリティを広げていく啓蒙活動をさらに行っていきたいです。『ユニウェブ』は当事者の「その先」に向き合うサポートツールになってまいります。
横山:ウェブアクセシビリティについて、どのような機能が実際に使われているのかを考えることは、今までどんな方々が困っていて、何が助けになるのかを考えることにつながります。障がいを持つ方々だけではなく、多くの人がウェブアクセシビリティの必要性を認識すれば、ユーザー側からの広がりも生まれるでしょう。その広がりは世の中を動かし、参入企業の数を増やすことにもつながるかもしれません。すべての人々が企業サイトを活用できる社会の実現のためにも、ウェブアクセシビリティの必要性が社会全体に認知されてほしいですね。
インタビュイー紹介

株式会社Kiva
代表取締役副社長
磯崎裕太さん
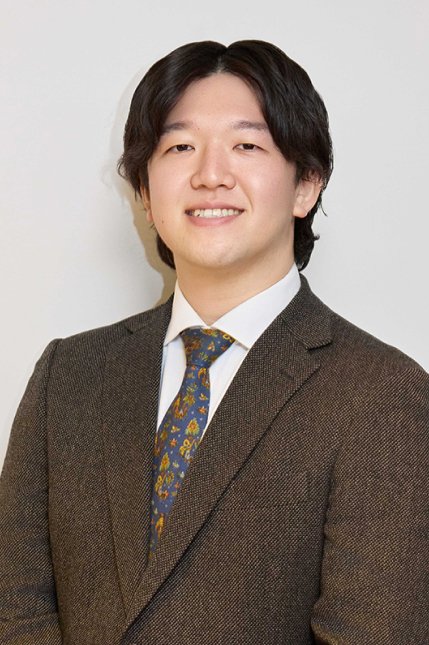
株式会社Kiva
法人営業部部長
齊藤太一さん
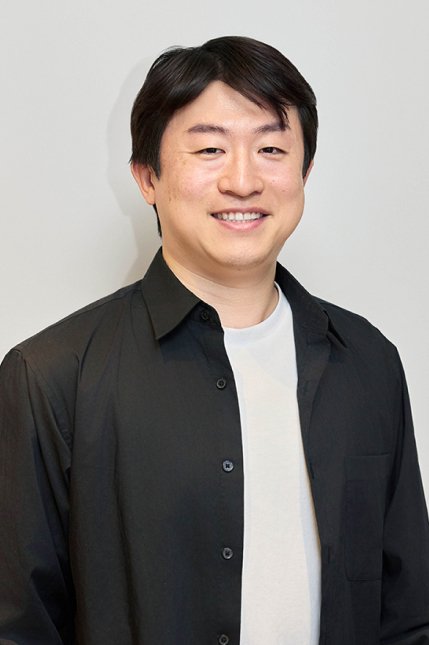
BIPROGY株式会社
プロダクトサービス本部
第六部 OBDサービス運用室企画課
横山正樹
前編「すべての人が、自分に最適なものを選べる状態とは?日本のウェブアクセシビリティ導入の壁に迫る――KivaとBIPROGYが『ユニウェブ』活用で目指す世界」はこちら



