羽田空港アプリはなぜ32万ものユーザーに使われるのか?―羽田空港の『今』を探り『明日』を創る、空港DX戦略対談【前編】
- 2025.06.30
- 特集

顧客体験(CX)向上にデジタルマーケティング戦略が果たせる役割とは何でしょうか。今回は、国内外から年間約8,000万人以上が訪れる、羽田空港旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う日本空港ビルデング株式会社が実践するCX向上戦略に着目。スマイルエックス合同会社代表/日本オムニチャネル協会フェロー・大西理氏をファシリテーターとして、日本空港ビルデング株式会社 旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ マーケティング戦略部長・中澤勝氏との対談を実施。前編では、公式アプリ「Haneda Airport」開発に至る背景や、データを起点とした顧客理解の深まり、ファン化戦略について掘り下げます。
後編「リテールメディアや共創拠点としてのポテンシャルも十分な"空港"という場所―羽田空港の『今』を探り『明日』を創る、空港DX戦略対談」はこちら
羽田空港アプリ「Haneda Airport」急成長の秘密

顧客目線の改善を積み重ねてきた現場経験から見えるものとは
――それぞれ自己紹介をお願いします。
中澤勝氏(以下、中澤):日本空港ビルデングのマーケティング戦略部で部長を務めております中澤と申します。大学卒業後、丸井グループに入社し、小売事業においてリーシングやプライベートブランドの企画、ECなどさまざまな業務を担当してきました。
取締役として小売部門全般を経験した後、2020年に日本空港ビルデングに入社しました。新設部署であるマーケティング戦略部担当として、空港という公共的な施設において、お客さまの利便性向上を実現させるだけでなく、目的に応じてさまざまなサービスをご利用いただくための会員サービスを展開しております。
大西理氏(以下、大西):私はカタログ通販企業でEC事業の立ち上げを担当したのをきっかけに、デジタルマーケティング全般に携わるようになりました。その後、さまざまな業種・業界でECやマーケティングを軸に、コミュニケーション、ブランディング、CRM領域のマネジメントなど幅広い分野での経験を積んでまいりました。
現在はこれらの経験を活かし、EC・マーケティング領域における課題整理や事業支援、チーム育成などの企業支援に携わっています。今日は中澤さんとの対談を通じて、さまざまな視点からお話ができればと思います。
空港に来る理由は「搭乗」だけではない。顧客理解からアプリ開発に至った経緯
大西:「Haneda Airport」導入の背景、手段としてアプリを選んだ理由についてお聞かせください。
中澤:当社は1953年に設立され、1955年に羽田空港での旅客ターミナル運営事業を開始しました。その後、成田空港の開港に伴い、ほとんどの国際線が成田空港からの発着となりましたが、2010年には再び羽田空港で国際線旅客ターミナルがオープンし、再国際化されました。
2020年3月に、第2ターミナル国際線施設が供用開始となった際に、羽田空港の国内線・国際線ホームページが統合されましたが、情報提供の重点は運航情報やアクセス情報といった「インフラとしての機能」でした。確かにインフラとしての機能を求める方が多い一方で、物販店舗や飲食店の情報を求める声もあることがアンケート調査から見えてきました。
大西:ユーザーニーズとWeb上での情報発信との間に乖離が生まれていたのですね。
中澤:そこで考えたのがアプリです。スマホ上で手軽に見たい情報を見ることができ、プッシュ通知でお知らせもできるアプリがあれば、顧客体験や収益の向上が期待できるのでは?と考えました。
大西:確かにホームページでは情報が散逸しやすく、運営上の社内調整や承認プロセスも複雑になりがちなので、アプリの方がユーザー・社内ともに使いやすいかもしれませんね。
中澤:もうひとつ大きかったのが、「情報のリアルタイム性」です。コロナ禍で店舗の閉店や営業時間の短縮などが頻発する中、アプリなら担当者が迅速に情報を更新でき、リアルタイム運用が現実的だと感じていました。
大西:アプリの導入にあたって、社内の理解はスムーズに得られたのでしょうか。
中澤:当時はコロナ禍において経営層も旅客に依存する事業体質に危機感を感じていた頃です。私たちはアプリ開発を進めたいというねらいのもと、空港利用に関するデータを集めることにしました。そしてInstagram公式アカウントのフォロワー約10万人(2020年当時)にアンケートへの回答を呼びかけたところ、1〜2週間で1300件超の回答が集まったのです。
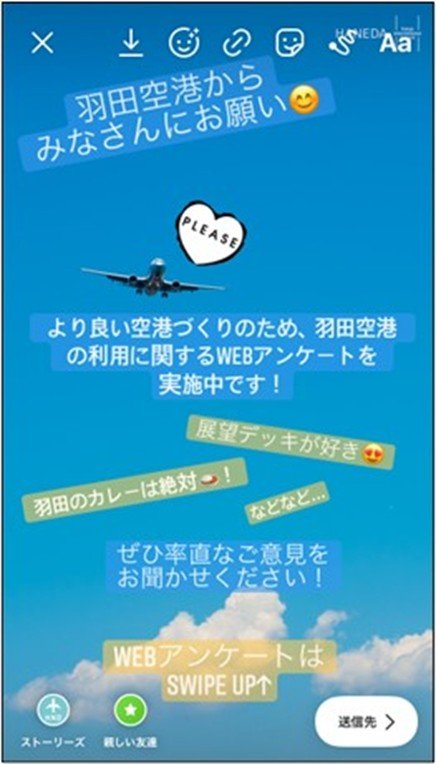
中澤:アンケートを取る前は、羽田空港のコア顧客はビジネスパーソンだと予想していましたが、実際にビジネス利用をしているのはわずか2割弱。大多数はレジャーで利用しており、また中でも驚いたのは「飛行機に乗らないタイミングでも羽田空港を利用する人」が6割近くもいたことです。もちろんアンケートをInstagramで行ったことによるユーザー属性の偏りはある程度見込んでいましたが、子どもの社会勉強に活用したり、カフェで仕事をしたりと、空港を「目的地」として訪れる人が多いことは大きな発見でした。
また、ビジネス・レジャー・ショッピング等の3用途が重複している人も多く、特に2つ以上の目的で訪れている人は物販店や飲食店の利用率が高いこともわかりました。
これらのアンケート結果は、アプリ導入における社内説得にも大いに貢献してくれました。
また羽田空港は敷地面積に限りがあるため、今後は旅客数以上に「購入率」や「客単価」を上げることが重要です。航空会社がマイルで顧客とつながっているように、空港もお客さまと直接関係を築く仕組みが必要だと社内で訴えたこともアプリ導入の決め手になったと思います。
大西:施策の実行には、「データの裏付け」が欠かせませんが、今回のアプリ導入は非常に理にかなった進め方ですね。顧客との関係性で言うと、羽田空港にはLTVの高いファンが多いことに驚きます。
中澤:そうですね。時間を要するアンケートにもたくさんの人が回答してくださり、ポジティブな意見もたくさん届きました。ファンの方々はSNS上で空港での良い体験を発信し、新たなお客さまを呼び込む存在にもなってくれます。その観点で、アプリ開発は目的ではなく、お客さまとつながる手段の一つとしてとらえています。
さまざまなサービスや施策によりアプリ認知を拡大し、32万DLを実現

大西:「Haneda Airport」のダウンロード数は、現在どのくらいなのでしょうか。
中澤:リリースから約4年で32万を超え(2025年4月現在)。MAU率も30%弱を維持しています。
大西:素晴らしいですね。空港では店舗の業態が多様で横断的な施策が難しいかと思いますが、ダウンロード促進には、どうアプローチされたのですか。
中澤:おっしゃるように店舗の業態は幅広く、また飛行機の時間が迫っているお客さまに丁寧な説明をするのは難しく、アプリの認知は大きな課題でした。空港内の待合スペースにQRコードを掲示したり、検査場上部のフライト情報モニターやサイネージで告知したりと細かく工夫しています。
購買行動の分析につながり、EX(従業員体験)も向上させるポイントサービス
中澤:現在、アプリのDL施策と並行して、購買データの分析も進めています。地方からのお客さまは観光・出張にかかわらずお土産の購買率が高い一方、関東圏の方は旅先での消費を優先し、空港内での購買は少ない傾向にあります。ただし、帰省する場合は羽田空港での購買率が大きくなるのが特徴です。また、商品やブランドの改善によって行動が変わる可能性も見えています。
ポイントサービス「HANEDAポイント」を導入したのは購買へのインセンティブだけでなく、購買行動の傾向を可視化することもねらいでした。現在は物販が対象ですが、今後は飲食にも拡大していく予定です。
さらに、アプリ会員証とポイントを連携させた「事後申請機能」により、購入後でもレシート情報を入力することでポイントを取得できるようにしました。
大西:時間がない時にレジで「今すぐ会員登録を」と言われるのはお客さまにとっても負担になりがちですが、事後申請可能なら前向きに受け止めてもらうことが増えますね。
中澤:そうですね。お土産店舗での1日当たりの取引件数はとても多いので、そのデータを取得できることで、マーケティングへの活用幅も広がっていくと考えています。
大西:アプリはあくまでツールの一つですが、それを多くの関係者と連携して運用していくことで、CXの向上だけでなく、テナント、パートナー企業といった関係者のEX(従業員体験)にもつながりますね。
ターミナルの間違いも指摘。「マイフライト」機能は羽田空港ならではの細やかさで好評
大西:アプリを運用してデータが取れるようになったからこそ気づいたことはありますか?
中澤:アプリでのデータ取得前もアンケートやインタビューにより顧客理解を深めてきたので、新たな気づきというよりは、データ収集によってさまざまな仮説を検証できるようになりました。
空港利用時に不安を感じる方が、半数以上にのぼることがアンケートから分かりました。特に大きいのは「飛行機に乗り遅れる不安」です。そこで、アプリに「マイフライト」機能を実装しました。
搭乗予定の便を登録するとターミナルや搭乗口、最寄りの保安検査場が表示され、ビーコンとの連動によりターミナルの間違いも通知されます。加えて、レストランやショップ情報の提供も実装し、来訪前から空港での行動を促すことができるようになりました。
マイフライト機能利用者に対し、プッシュ通知でNPS調査を行ったところ、アプリで紹介した店舗を利用した割合は約30%と、行動喚起の効果が表れました。蓄積されたデータを活かすことで、よりパーソナライズされたサービスが展開できることが見込めたのです。今後はさらに個別の利用傾向も把握できるようになると考えています。
ポイントシステム再構築、インバウンド向けアプリ......利用者をさらに惹きつける「仕掛け」

「空港に行かなくても使いたくなる」EC連携でアプリと顧客の接点をさらに拡大
大西:さらに「Haneda Airport」アプリを発展させるために、新たな施策は考えているのですか。
中澤:ポイント付与が「マイフライト」の利用促進につながり、空港体験の向上にも効果が確認できました。今後はECとの連携も含め、ポイントサービスの拡充を検討しています。
大西:空港に頻繁に来られないお客さまにも「ポイントを使ってECを利用してみよう」と思ってもらえる仕組みですね。ところで、インバウンド需要が非常に高まっていますが、外国人旅行者に対してはどのようにアプローチできるとお考えでしょうか?
中澤:当初はGDPR(EU一般データ保護規則)への配慮から、日本国内のアカウントのみ、ダウンロード可能な設定にしていました。インバウンド対応の必要性は強いことは分かっていたのですが、既存のプラットフォームでは多言語対応が難しかったため、インバウンド向けに別アプリをネイティブで開発し昨年秋にリリースしました。大規模な告知はしていないものの、DL数は着実に増加しています。
インタビュイー紹介

日本空港ビルデング株式会社
旅客ターミナル運営本部
リテール営業グループ
マーケティング戦略部長
中澤勝さん

スマイルエックス合同会社CEO
日本オムニチャネル協会フェロー
大西理さん
後編「リテールメディアや共創拠点としてのポテンシャルも十分な"空港"という場所―羽田空港の『今』を探り『明日』を創る、空港DX戦略対談」はこちら



