「DX for CX」の真意とは? アパレルの未来を見据える
オンワードデジタルラボが実現した新たな顧客体験【前編】
- 2025.09.01
- 特集

「23区」や「組曲」など数々の人気ブランドを展開するオンワード樫山。グループ全体のデジタル戦略を担うオンワードデジタルラボは、DX推進とCX向上の両立を目指し、アパレル業界に新たな潮流を生み出しています。今回は、オンワードデジタルラボ代表取締役社長 山下哲氏と、スマイルエックス合同会社CEO/日本オムニチャネル協会フェローの大西理氏による対談を実施。OMO施策や会員基盤の整備などの多角的なテーマから、オンワードが描く次世代の顧客体験設計について語っていただきました。前編では、オンワードデジタルラボ立ち上げの背景や、DXで顧客体験を重視する理由が話題となりました。
後編「OMOによって生まれた「デジタル上の棚」で店舗の力を最大化ーオンワードデジタルラボが実現した新たな顧客体験」はこちら
リアルもデジタルも、重要なのは"顧客基点"

アパレル業界におけるデジタル化の先駆者
――自己紹介をお願いします。
山下哲氏(以下、山下):2006年に新卒でオンワード樫山に入社し、最初の5年間はメンズブランドの営業を担当しました。その後EC部門に異動し、プラットフォーム開発に携わってきました。
2020年からオンワードデジタルラボ(以下、デジタルラボ)に出向し、現在は代表取締役社長です。オンワード樫山のEC事業も引き続き管轄しており、2024年10月にオンワードホールディングスがM&Aしたウィゴー ではCDOを兼任している他、会員基盤整備や人材採用などにも関わっています。
大西さんとの出会いは2018年。CRMやOMOについて貴重な助言をいただきました。
内製か外部登用か。オンワードが選んだデジタル組織のカタチ
大西:デジタルラボが設立されたのは2019年3月です。グループ全体のDX推進という課題意識が起点だった印象です。商品企画や販売などの中核業務とECやデジタルマーケティングでは、必要なスキルや思考がまったく異なります。本体からの人材異動では適応が難しく、受け入れ側もマネジメントに苦労することが多いですよね。
その点で、デジタルラボが外部から専門人材を採用して適切なポジションに配置したのは、理にかなっていたと思います。そして、将来的にはアパレル業界全体への波及も見据えていたのではないでしょうか。
山下:その通りですね。その一方、人材登用の仕方にはいろいろな可能性があるとも感じますね。自社プロダクトの背景や価値の理解度はパフォーマンスに直結します。外部の専門人材が活躍する場面もありますが、営業やMDを経験してきた生え抜きの社員なら、商品理解をもとにデジタル領域でも力を発揮し、顧客へ価値を伝えることができますから。
大西:アパレルメーカーとしては、やはり「ブランドビジネスとしての立ち位置」が大前提ですよね。その上で、接客や販売など、お客さまとのコミュニケーションに関し、デジタルをどう活用していくが重要になりますが、オンワードグループ全体の中でのデジタルラボの立ち位置はどのようなものなのでしょうか。
山下:これまで築いてきた顧客基盤や仕組みづくりのノウハウや実績をベースに、グループ各社とより密な関係性を築いていければと思っています。とはいえ、デジタルラボがどこまで各社の成長やPLにコミットできるかについては、まだ手探りの部分もありますね。
ECは一販売チャネルではなく、CXを支える場

大西:デジタルラボは「DX for CX」(DXは良い顧客体験を実現するためにある)を掲げています。CXをあえて前面に出している意図はどこにあるのでしょうか。
山下:弊社にはもともと、顧客を大切にする文化があります。店舗でもECサイト「ONWARD CROSSET」でも、お客さまとの接点がすべての基点。より良い「おもてなし」の手段がDXだと考えています。
大西:「ONWARD CROSSET」立ち上げ当初から、顧客第一の姿勢があったのですね。
山下:はい。ただ私自身に関して言えば、意識が大きく変わったのはデジタルラボに出向してからです。以前は、近視眼的に担当部署の個別最適を求める気持ちが強く、売上を追求することが第一優先になっていました。しかし、会員プログラムやOMOに深く関わるようになってからは、オンワードがこれまで築き上げた強い会員基盤に支えられていることを実感するようになりました。
以来、サービス設計の基準は「お客さまに喜んでもらえるか」。ECを単なる販売チャネルではなく顧客体験を支えるサービスとして捉えるようになっています。
「オンワードメンバーズ」600万人突破の秘訣
大西:メンバーシップサービス「オンワードメンバーズ」の会員数が600万人を突破したとのことですが、会員基盤構築について聞かせてください。
山下:会員基盤の整備は、2014年頃から進めています。それまでブランドや店舗ごとに行っていた顧客管理を一元化する方針のもと進めたのが出発点です。
大西:オンワードの場合、もともとリアル店舗についていた"根強いファンを一元化した"のが特徴ですね。
山下:EC事業がここまで成長したのも、既存のブランド力と店舗スタッフによる顧客接点があったからこそです。2020年にはECと店舗の会員プログラムを統合 し、どちらからでも同様にポイントなどが使える仕組みにしました。
大西:今ではCRMの活用が進み、会員をセグメントごとに分析できるようになりましたね。
山下:新規・既存・リピーター・復活顧客などに分類し、継続率やF2(2回目購入率)を追うなど、顧客構造を把握した上で施策を設計しています。また、店舗からECへのチャネル転換も見えるようになり、LTV向上にもつながっています。
コロナ禍で増えたEC利用が、その後も伸び続ける理由
大西:会員数600万人に至る中で、特に伸びたタイミングはありましたか?
山下:導入初年度から2年目までは急増期でしたが、その後は年50〜60万人増ペースで安定しています。「ONWARD CROSSET」の購買が大きく伸びたのは2020〜2021年、コロナ禍で店舗営業が難しくなっていた時期です。対面での買い物がしづらい状況でも「このブランドが欲しい」とECサイトを訪れたお客様が多くいらっしゃいました。
その後はただ数字を追うのではなく、どの層からどのように客数を増やすかという構造的な視点が求められました。コロナが明ければEC購買は減るとの予想もあった中、2022年以降も購買人数を維持できたのは大きな成果でした。
大西:コロナ禍で外出できないから仕方なくECを使ったというところから、「今後も使い続けたい」とお客さまに感じてもらえたことがポイントですね。「ONWARD CROSSET」は品揃えやコーディネート提案も充実していて、店舗とは異なる価値を提供できていたのではないでしょうか。
また、「ONWARD CROSSET」を自社ブランドだけでなく他ブランドも扱うモール型自社ECに進化させた点も大きかったと私は感じています。オンワードのように、ブランド力と顧客との信頼関係があってこそ成立するモデルではないかと思うのです。
山下:その側面もあったと思います。自社ブランドだけでなく、バッグやアクセサリーなど、自社であまり扱っていなかった領域のブランドを取りそろえるように強化し始めたのが2017年頃です。お客さまのニーズを見極め、購買体験にプラスの価値を提供することを狙ったのです。ユーザーインタビューからも、品質への信頼感を抱いてくださっているお客さまが多いことがわかっています。
大西:価格に見合う価値を提供し続けているからこそ、高いロイヤルティを得られているのでしょうね。
EC化率29%を支えるデータドリブンな顧客体験設計

「在庫戦略」と「アプリ導線」を掛け合わせEC売上が急加速
大西:EC事業の売上高(2025年2月期)は前期比9.2%増の516億5900万円、EC化率も29%と 業界内でも高水準です。成長し続けている要因は何でしょうか。
山下:一つには、サイトのユーザビリティ向上が挙げられます。2015年以降、商品との出会いや購買検討の場としてECを整備してきました。
もう一つは在庫管理の改善です。「ONWARD CROSSET」立ち上げ当初はアナログなオペレーションが多かったのですが、デジタル化を進め、例えばEC倉庫に在庫がない商品でも販売できるようにするなど、裏側の強化も図ってきました。
徐々に販売実績が積み重なってきて、ブランド側もEC向けの商品供給量を増やすようになっています。結果としてお客さまの利便性向上とブランドの成長の両方につながったと感じています。
大西:コロナ前の2015〜2020年の間に行われたクロスユース(店舗とECの併用)への取り組みも印象的でしたね。
山下:そのキーポイントも在庫戦略にありました。標準よりも大きめ・小さめのサイズはニーズが高いにもかかわらず、店頭ではスペースの関係で取り扱いが限られていました。そこでEC限定展開を始めたところ、高い反響があり、店舗展開にもつながる好循環が生まれたのです。
2018年に導入したアプリの効果も大きいですね。熱心なお客さまほど、アプリを積極的にインストールする傾向があります。アプリ経由でデジタルに触れていただく機会が増えたことで、EC利用率も上がっていきました。
大西:店舗を利用されるお客さまにメールを送っても、開封率はなかなか上がりません。一方アプリだと、多くの方に会員証として常時使用されるので、プッシュ通知で新着商品や値下げ情報が表示されれば、「試してみようかな」と思っていただける。そのような導線で、初めてのEC購入につながるケースが多いのではないでしょうか。
例えば在庫が「残りわずか」と表示されていると「今買っておこう」という意思決定がなされやすくなります。こうした仕掛けが、EC活用を自然に定着させていくように思います。
山下:さらに、コーディネート投稿の閲覧数やスタッフ別売上などを可視化することで、スタッフのモチベーション向上にもつながりました。数字が見えることで「自分の投稿が価値を生んでいる」と感じられるようになったのだと考えています。
インタビュイー紹介

株式会社オンワードデジタルラボ代表取締役社長
株式会社オンワード樫山EC戦略グループ長
株式会社ウィゴー取締役 CDO兼任
山下哲さん
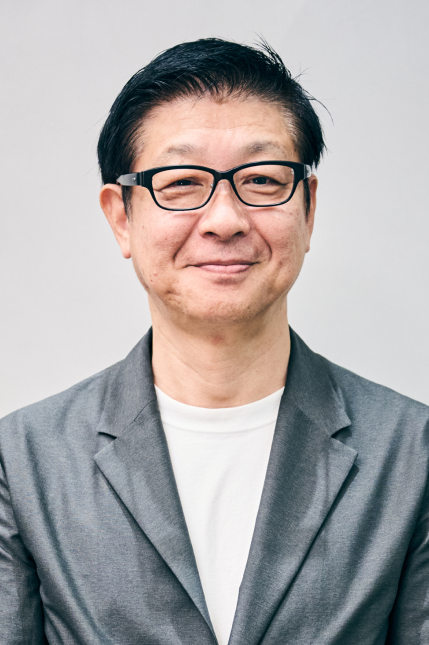
スマイルエックス合同会社CEO
日本オムニチャネル協会フェロー
大西理さん
後編「OMOによって生まれた「デジタル上の棚」で店舗の力を最大化ーオンワードデジタルラボが実現した新たな顧客体験」はこちら



