OMOによって生まれた「デジタル上の棚」で店舗の力を最大化―オンワードデジタルラボが実現した新たな顧客体験【後編】
- 2025.09.08
- 特集

OMO型試着サービス「クリック&トライ」や複合型店舗「オンワード・クローゼットセレクト」など、リアルとデジタルを横断した取り組みを展開するオンワード 。後編では、OMO戦略に込められた顧客体験設計の意図や、ブランド横断の店舗展開、変化する購買行動への対応策などが語られました。参加者は前編に続き、株式会社オンワードデジタルラボ 代表取締役社長 山下哲氏と、スマイルエックス合同会社CEO/日本オムニチャネル協会フェロー 大西理氏のお二人です。
前編「『DX for CX』の真意とは?アパレルの未来を見据えるオンワードデジタルラボが実現した新たな顧客体験」はこちら
ブランド力とテクノロジーが生んだOMO戦略

地方店舗から始まった「クリック&トライ」誕生秘話
大西:OMO型の店舗試着サービス「クリック&トライ」はどんな経緯で始まったのですか?
山下:「クリック&トライ」は自社EC「ONWARD CROSSET」で気になる商品を選び、希望店舗で試着・購入できるサービスです。テストリリースは2020年秋、コロナ禍でECにトラフィックが集中していたタイミングで、ECから店舗へ送客できないかという発想からスタートしました。特徴的なのは、ブランド横断で商品を揃えられる点です。従来のようにブランド単位で店舗運営するのではなく、複数ブランドを組み合わせてスタッフの提案力と販売効率を高める狙いがありました。実は「クリック&トライ」は地方店舗のニーズから生まれたサービスで、お客さま一人ひとりに合わせて商品を用意するアナログな運用から始めました。
以前は「ネット上に在庫があっても、店舗では取り扱いがない」という状況が多々あり、販売スタッフも歯がゆい思いをしていました。「クリック&トライ」を導入することで、スタッフが裁量を持って商品を取り寄せ、お客さまに最適な提案をできるようになったのです。
大西:リアル店舗の省スペース化が進む中で、店頭に置けない商品を提案できると「デジタル上の棚」が広がりますね。そして店舗が本来持っている力を、オンラインによって拡張させた。それが「クリック&トライ」の本質ですね。
山下:はい。デジタル化で在庫が可視化され、「商品がいつ、どこに動いているのか」が見えると、アパレルのECは強くなるのだと実感しましたね。システムや業務フローの調整はかなり大変でしたが、内製と外部委託を組み合わせて柔軟に体制を組み、現場の声を反映しながら素早く改善できたことで、導入のスピード感も担保できました。
大西:成果はどのような形で現れているのですか。
山下:導入店舗と非導入店舗で、明らかに売上の差が出ています。特に大きいのは、スタッフがこの仕組みに能動的に関わっていることです。お客さまに喜ばれる実感があるので、接客のモチベーションも上がり、成果につながっています。
DXとは、人の意識そのものを変えていくこと

大西:「クリック&トライ」の導入は今、どのくらいまで進んでいるのですか。
山下:2024年度末時点でオンワード樫山全体の64%の店舗に導入済みです。今後もさらに拡大し、全店導入を目指しています。また、複数ブランドを扱う店舗「オンワード・クローゼットセレクト」も2020年にテスト導入し、2021年から本格展開しました。ECサイト「ONWARD CROSSET」と同じく、ブランド横断で商品提案ができる設計になっていて、今後さらに店舗数を増やしていく方針です。
大西:ブランドの垣根を越えることに対し、現場に抵抗感はないのでしょうか?
山下:当初は「自分のブランドをどう守るか」といった声もありました。でも、実際にお客さまからの反応や来店頻度の変化を実感するうちに、スタッフ自身が意義を感じるようになっていったようです。以前は「ネットは苦手」と言っていたスタッフが、今では積極的に「クリック&トライ」を活用しているケースも出ています。DXとはただ業務改革することではなく、「人の意識そのものを変えていくもの」だと感じますね。
大西:モール型施設に出店する場合、1ブランドでは売り場面積を確保しづらいですよね。複合型の方が合理的という印象もあります。
山下:そうですね。例えば20坪ずつ5ブランドを出していたものを、100坪の複合店舗として統合すれば、坪効率が上がり、施設側にとってもメリットがあります。スタッフも一箇所に集約でき、他ブランドの商品知識を持つことで提案の幅も広がるのでキュレーターのような役割を担える。社内・取引先・お客さまの「三方良し」構造が実現できるのです。
大西:各ブランドにはそれぞれの個性があるとはいえ、「オンワード」の看板を前面に出せることの効果も大きいですね。顧客管理の一元化にも生きてきます。ブランドの入れ替えがあったとしても、オンワードという母体がしっかりしているからこそ、安心感が保たれるのだと思います。
人が育ち、体験が進化する。アパレルDXの未来

アパレルDXの鍵は「体験をデザインすること」
大西:これからのアパレルEC市場をどう見ていますか。
山下:これまで一般的だった「SNSで発信し、自社ECに誘導する」という動線は、今後は成立しにくくなる時代が来るかもしれません。それぞれのチャネルの役割や意義を見直し、再定義する必要があると感じています。
大西:先日参加したシンガポールで開催された「NRF APAC 2025(小売業界イベント)」
で印象的だったのが、「ハイブリッドコンシューマー」という言葉です。消費者は今やSNS、EC、リアル店舗を自在に行き来していますから、小売側は「インテリジェント・リテーラー」として、データを活用し、摩擦のない購買体験を設計する力が求められています。
ASEANではすでに、SNSから直接購入するユーザーが4〜5割に達している企業もあり、日本もこの流れに乗っていくはずです。今後は、未来の購買体験を構想できる人材の重要性がますます高まるでしょう。
山下:個人的にイノベーションを予感しているのは、「TikTokコマース」です。海外ではすでに成果が出ており、日本でも本格導入が始まっています。商品との出会いから購入までをTikTok画面上で完結させるような、まったく新しい購買体験につながる可能性があると考えています。
大西:TikTokコマースのようなものが普及すると、「会員」という概念すら変わってくるかもしれませんね。「誰が買うか」より「どんな行動をするか」で体験が設計される。SNS上で出会いと購買が完結する中では、会員登録自体が不要になる世界が来るかもしれません。
山下:SNS、自社EC、モール、実店舗は敵対する構造ではなく、それぞれのチャネルで想定すべきターゲットも役割も異なります。どこで何を発信するのかをもう一度考え直さなくてはいけないと思います。
大西:デジタルでも、「答えは現場にある」点は店舗と同じですから、まず自分がユーザーとして試すという姿勢は大事ですよね。新しいアプリやAIなど、自分でテクノロジーを使ってみないと本質的な提案にはつながりません。年齢に関係なく、体験する意欲こそがDX時代の基本だと思います。
オンワードの多様な資産と接点を活かすために
山下:オンワードとして直面している課題の一つが、若年層におけるブランド認知の低下です。だからこそ、Z世代に人気のあるウィゴーをグループ会社化したことには大きな意味があったと捉えています。
大西:若者は価格帯やブランドイメージに敏感です。若年層向けに新ブランドを立ち上げるよりも、すでに支持されているブランドを活用する方が、接点を持つ上では合理的でしょう。ウィゴーの子会社化はその好例だと思います。
山下:今後はオンワード樫山単体での発信にとどまらず、ペット用品やオーダースーツなど、グループ全体の資産を活かしていきたいですね。ポテンシャルの高い分野がまだまだあるので、共通の会員基盤をCRM施策に生かし、デジタルを通じて「まずは体験してもらう」ことを増やしていく。それが、会社として次の成長のために必要なことだと考えています。
育成の鍵は「場づくり」。オンワード流デジタル人材の伸ばし方

大西:最近は、デジタルスキルを身につけて独立や転職する人も増えていますが、デジタルラボとして人材に関してはどう見ていますか?
山下:デジタル人材をずっと自社で抱え込む必要はないと思っています。ただ、培ったスキルを顧客もブランドの価値観も違う他社で100%活かせるかというと、正直難しいでしょう。「オンワードだから活きたスキルだった」と感じる部分も多いかもしれません。残りの部分は、その人の経験やチャレンジの質によると思います。
大西:店舗の現場出身者がデジタル部門で経験を積み、またブランド側に戻る流れもあるのでしょうか。
山下:むしろそれが理想的な形だと思っています。例えばウィゴーには、必要に応じてデジタルラボのメンバーをスポット的にアサインしています。そしてそこでの実践知をデジタルラボに持ち帰って生かす。そんな循環をもっと活性化させたいですね。
大西:プロジェクト単位で人をアサインする仕組みもユニークですね。
山下:大きなプロジェクトは社内公募しており、PMは中堅社員が担っています。私も過去に2度、システムリプレイスのPMを経験しましたが、非常に成長できて力がついたと感じました。
大西:アパレルもITも好きな人にとって、戦えるフィールドがあること自体が希望になりますね。今後もデジタルラボが業界にとって大きな存在になっていくことを期待しています。
インタビュイー紹介

株式会社オンワードデジタルラボ代表取締役社長
株式会社オンワード樫山EC戦略グループ長
株式会社ウィゴー取締役 CDO兼任
山下哲さん
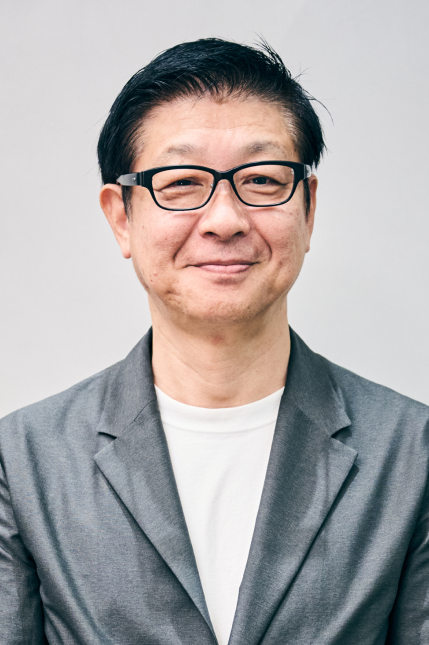
スマイルエックス合同会社CEO
日本オムニチャネル協会フェロー
大西理さん
前編「『DX for CX』の真意とは?アパレルの未来を見据えるオンワードデジタルラボが実現した新たな顧客体験」はこちら



