すべての人が、自分に最適なものを選べる状態とは?日本のウェブアクセシビリティ導入の壁に迫る――KivaとBIPROGYが『ユニウェブ』活用で目指す世界【前編】
- 2025.03.14
- 特集

情報提供やブランドとしての価値の発信、商品の販売など、企業にとって自社のウェブサイトやECサイトは、生活者とのコミュニケーションにおける重要なツールとなっています。しかしそこにある情報は、果たして本当にすべての人々に届けられているでしょうか?今回、ウェブアクセシビリティツール『ユニウェブ』を展開する株式会社KivaとBIPROGYとの対談インタビューが実現。前編では、日本のウェブアクセシビリティの現状や課題について意見が交わされました。
後編「ウェブアクセシビリティが当たり前の社会をともに実現する――KivaとBIPROGYが『ユニウェブ』活用で目指す世界」はこちら
国内400万人が抱えるウェブサイトの使いにくさ。高まるウェブアクセシビリティのニーズ

年齢や身体的条件に関わらず、全ての人が平等にウェブサイトを利用できるために
――それぞれ自己紹介をお願いします。
磯崎裕太(以下、磯崎):株式会社Kiva代表取締役副社長、磯崎と申します。主に開発部門を担当しつつ、採用や営業も兼任しています。創業まではメガベンチャーなどでエンジニアとしてBtoC、BtoBの業務システムに携わっていました。
齊藤太一(以下、齊藤):同じく株式会社Kivaの齊藤と申します。私はセールスとして、エンタープライズの新しいお客様を担当しています。これまで大手人材派遣企業の法人営業などの仕事をしていました。
横山正樹(以下、横山):BIPROGYの横山と申します。SaaS型OMOプラットフォームOBD(Omni-Base for DIGITAL'ATELIER)のプロダクト管理チームに所属し、全体の問題解決や効率化を担っております。新卒入社してすぐの頃はソフトウェアエンジニアとしてメガバンクを担当し、その後はJava中心の部署で社内用ツール制作などいろいろと経験を積みました。
――Kiva様の事業内容について教えてください。
磯崎:現在、Kivaの事業は主に2つあります。まずは『proteger(プロテジャー)』というECサイト向け延長保証サービスです。弊社のAPIを組み込んでいただくことで、家電量販店での買い物と同様に、ECサイトで購入した商品に延長保証を付帯することができるものとなっています。そしてもう1つが、現在の主力商品であるウェブアクセシビリティツール『ユニウェブ』です。
齊藤:ウェブアクセシビリティとは、年齢や身体的条件に関わらず、全ての人が平等にウェブサイトを利用できることを指します。例えば、老眼のあるご高齢の方にとっては、文字が小さいサイトは利用しにくいですよね。他にも、視覚や聴覚の障がいなどのさまざまな理由により、ウェブアクセシビリティは多くの方に求められています。その数は現在、国内だけでも400万人以上ともいわれています。
またウェブアクセシビリティには、世界的に規格要件が設けられています。例えば、文字サイズや音声の読み上げ、色のコントラストなどで、現時点での規格の数は50に及びます。
海外では訴訟事例も。後れを取る日本のウェブアクセシビリティ
――日本でウェブアクセシビリティが求められるようになったことには、どのような背景があるのでしょうか?
磯崎:既に、アメリカではウェブアクセシビリティが不十分な企業に対して訴訟が起き、賠償も発生しています。2025年6月にはEAA法(欧州アクセシビリティ法)が施行となり、ヨーロッパ全体でウェブアクセシビリティの実装が義務化されることが決まりました。この流れは今後、世界的に加速すると考えています。
横山:ここ数年、多くの企業がIRサイトでSDGsやサステナビリティを掲げていますよね。それは、海外ではSDGsについて「対応している企業が評価される」フェーズから、「そもそも対応していないと評価されない」フェーズに移り変わっているからです。ウェブアクセシビリティも、同じ流れをたどるのではないかと考えます。

齊藤:日本では2024年に改正障害者差別解消法が施行され、企業サイトは設けられた規格を満たすことが求められるようになりました。しかし、以前から義務化されていた自治体やコーポレート系のサイトなどを除き、一般企業のウェブサイトではまだほとんど対応されていないのが現状です。
――今後、日本の企業サイトもウェブアクセシビリティに対応していく流れとなるのでしょうか?
磯崎:はい。しかし、例えば文字サイズの調整ひとつをとっても、規格を確認して「この文字はこのくらい大きくしなければいけない」などと判断していくこと、そしてサイトの1ページずつ修正していくことは大変多くの工数が必要です。ECサイトであれば、ゆうに100ページ以上の作業が発生するでしょう。それは、時間の面からも人材確保の面からも、負担が大き過ぎます。『ユニウェブ』は、その課題をクリアにするという思想で開発しました。
横山:システムを多くの企業様に提供している当社の立場から言えば、現状のウェブサイトをすべてウェブアクセシビリティ対応に修正するのは、率直に言ってハードルが高い状況にあります。数百万円単位のコストがかかりますし、プロダクトの成長に伴って、サイト画面も成長する。また、今後も国が求める規格の内容にも、変更や追加があるでしょう。その点、『ユニウェブ』は機能数が圧倒的ですし、パッケージ買い切りではなくサービスとして提供され、規格のアップデートにも対応される。魅力的なサービスだと感じています。
磯崎:『ユニウェブ』の開発については、海外にウェブアクセシビリティに関する先行事例が多かったことに加えて、改正障害者差別解消法の施行が大きなきっかけとなりました。
『ユニウェブ』で企業のこだわりを損なうことなくウェブサイトの使いやすさを実現する
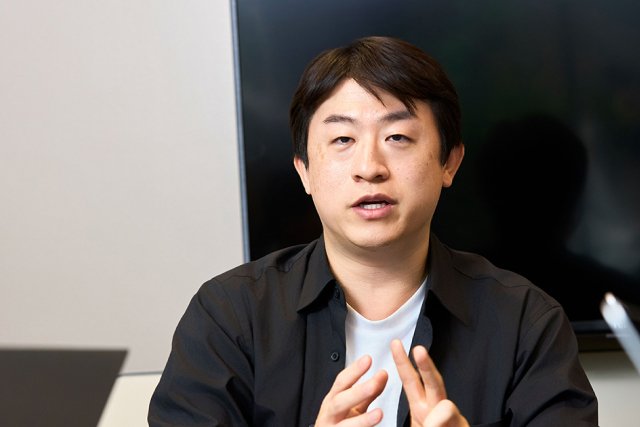
「自分に最適な選択肢がある」という状態が重要
横山:「ウェブアクセシビリティ」という言葉は、世間一般の方々はもちろん、IT業界の方々でも、正確に把握できていない方もいらっしゃるでしょう。ウェブに限定しないところでは「ユニバーサルデザイン」という言葉もありますよね。
磯崎:ウェブアクセシビリティとユニバーサルデザインは、目指すゴールが異なると認識しています。ユニバーサルデザインは「いろいろな価値観や特性を持った人が一緒にいる」という状態を目指すものです。一方ウェブアクセシビリティは、何らかのハンディキャップを持った状態の方々をサポートするものです。重なる領域はありますが、別の方向性も持った概念だと考えています。
――業種によっては、サイトのデザインや色味などにこだわりを持つ企業もあると思います。『ユニウェブ』を展開するにあたり、注意していることや意識していることはありますか?
磯崎:確かに、デザインが標準化され「どのサイトも色味は同じ」となると、企業のカラーが出せません。例えば、アミューズメント業界においてアニメの特設サイトの色味を調整することは、表現を奪うことにもなります。また、アパレルブランドなどは色味にこだわりを持つ企業も多いでしょう。『ユニウェブ』はそういった企業に制約を設けるものではなく、サイトを見る個人が各自の手元で自分に合った設定をするものですので、基本的には誰も不利益を被らない状態を作ることができます。
横山:どちらかの側に寄せ過ぎてしまうと、他方に制約が生まれる。それは本当の意味でのウェブアクセシビリティではないですよね。障がい者や生活のしづらさを持つ方への配慮がされたものが、選択肢の中にある。「いろいろな人が、自分に最適なものを選べる状態である」ということが大切なのですね。
ユニウェブを活用すれば、例えば自分に視覚障害があると自覚していない方も「なんとなく見えにくいな」と手元で調整することができます。明らかな「障がい」とまでは言えない、健常との境界にいるような方々も、自分に合わせた調整ができる。選択の幅があるということは、そういった意味でも重要です。
磯崎:おっしゃる通りです。弊社にも実は、身体障害者手帳までは持っていないけれども、見えづらさを持つスタッフがいます。ウェブアクセシビリティが広まるということは、そういった方々が当然に情報にアクセスできる環境が実現するということですね。
インタビュイー紹介

株式会社Kiva
代表取締役副社長
磯崎裕太さん
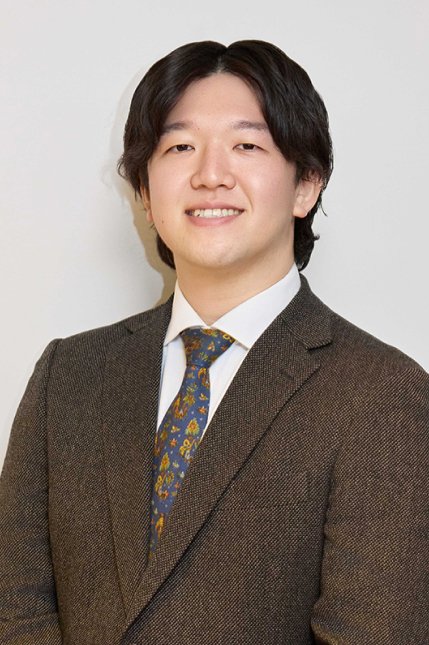
株式会社Kiva
法人営業部部長
齊藤太一さん
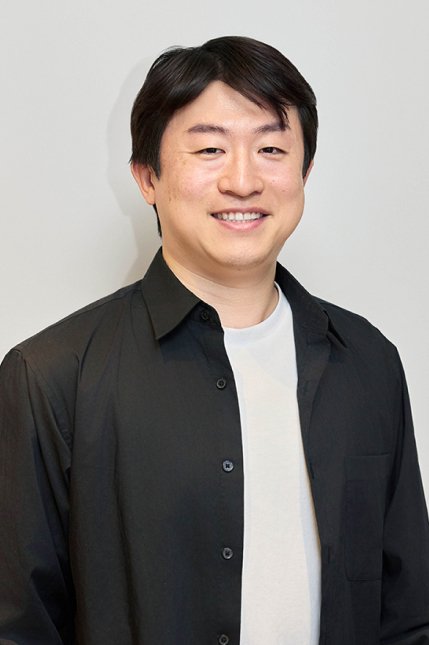
BIPROGY株式会社
プロダクトサービス本部
第六部 OBDサービス運用室企画課
横山正樹
後編「ウェブアクセシビリティが当たり前の社会をともに実現する――KivaとBIPROGYが『ユニウェブ』活用で目指す世界」はこちら



